 |
| 赤堀家の紋(三つ頭左巴) |
 第10回 第10回 |
| (赤堀在住の青砥様の資料より編集したものです) |
天正の大地震
この地震は天正13年11月29日(1586年1月18日)午後10時に起きM8クラスで陸域の浅い地震と考えられ、その規模は非常に大きなものと推定されている。岐阜県ほぼ全域、富山県西部、滋賀県東部、名古屋市などで震度6相当と推定される。(図6-24)。飛騨白川谷の保木脇で大山崩れがあり帰雲城が埋没して城主以下多数が圧死した。白川谷全体では倒れた家が300余という。越中木船城(高岡市の南西)では、城主以下多数が圧死したとされる。その他大垣、尾張の長島、近江の長浜、京都などでも被害が生じた。余震は翌天正14年1月(1586年)まで頻発した。京都でも約1年間余震が感じられた。尾張、伊勢の海岸付近では液状化現象があったと思われる記録が見られる。また伊勢湾で津波があったような記録もある。 |
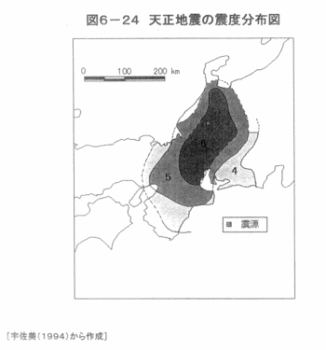 |
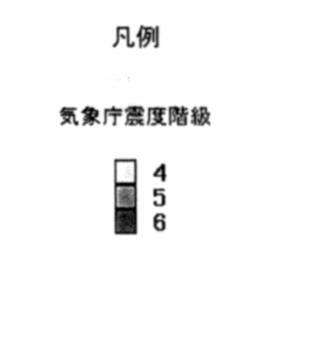 |
| 震源域については、庄川断層帯(御母衣断層帯を含む)付近から阿寺断層帯付近にかけてとする見方が強い。伊勢湾奥付近の活断層(養老ー桑名ー四日市断層帯など)もこのとき一緒に活動したとする考えもある。この地震については現在もいろいろ調査されているが不明な点が多い。なおこの地震で家屋の倒壊14000軒を越し、死者9000人を数えた。 |
なお三重県史の年表には天正13年10月伊勢両宮正遷宮。内宮は124年ぶりに復興。
11月近畿、東海に大地震発生、津波も発生する。
この年筒井定次大和の国より伊賀の国に国替えとある。
平成15年出土した五輪の塔は地下1.5mに埋没していたのは地震の液状化が原因ではないかと思われます。
この埋没した上に村人が過去の死者を埋葬し、3m位の土盛りの上に秋葉権現の社を建てたのではないかと思われますが記録も言い伝えもないので分かりません。
日永-堀木線道路建設前に、城東町の発掘をされたとき、大人、子供の裸足(はだし)の足跡が発見されたのはこの地震のさいの足跡とも推測できる。 |
 |
| 出土した五輪の塔の一部 |
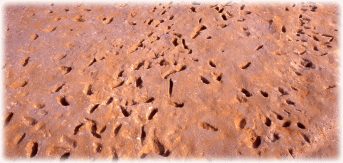 |
| 右往左往した子供と大人の足跡 |
| 『家忠日記』には岡崎城も地震で壊れてその普請を日記に次のように記している。 |
| 一 日 |
|
城へ出候、なへゆり候 |
| 二 日 |
|
なへゆる、岡普請出候て、ふかうすかへり候、たうめ之御とりたて候ハん由候、(略) |
| 三 日 |
|
なへゆる、喜平所ニ ふる舞候、 |
| 四 日 |
|
なへゆる、とうへくわたて候、天清兵衛被越候 |
| 五 日 |
|
雨降、なへゆる |
| 六 日 |
|
なへゆる、 (略) |
| 七 日 |
|
なへゆる、普請候、奉行鵜殿善六、安藤金助、吹雪市右衛門、 |
| 八 日 |
|
同なへゆる |
| 九 日 |
|
なへゆる、夜雨降、戸三郎右衛門殿見舞二被越候、 |
|
など翌三月毎日のように地震の記録を見ることができる。
あわせて「普請」の記述も見える。地震によって、建物に亀裂が入ったり、傾いたりしたことも考えられる。城普請に大きな責任を負っていた家忠は、各所を見て回っていたことだろう。
「岡普請出候」とは地震で破損した岡崎城の修理が完了したものと思われる。
「なへ」とは地震のことで「ゆる」とは揺れること。 |
 |
| 参考 「家忠」は松平家忠のことで天正五年(1577年)から文禄三年(1594年)まで18年間にわたって書かれた日記。関が原の合戦(1600年)で伏見城を守るも石田三成に攻められ戦死。享年45歳。 |
| 次回11回赤堀城の年表 |
|
|
|
|
 |
訂正 第1回の記述で治承4年(1180)史上名高い宇治川のッ先陣(源義経軍の佐々木高綱と梶原景季の先陣争いをして木曾義仲軍を破った戦い)を下記に訂正いたします。
治承4年源頼政が以仁王を奉じて平家に反旗を翻し反乱を起こした。それを討たんとして平家方の足利又太郎忠綱が宇治川を馬筏を組んで渡河した功により上野国(群馬県)赤堀荘を賜った。とお詫びの上訂正いたします。
 
|